手取りと年収のリアルを一緒に学ぶ【第7回】
「給料は上がってるはずなのに、手取りが少ない気がする…」
そんな風に感じたこと、ありませんか?
この記事では、**給与明細の“控除欄”**に注目し、ひとつずつの意味や背景を丁寧に読み解いていきます。
実例やシミュレーションを交えて、一緒に「見える化」していきましょう!
🔍 給与明細の構成をざっくり理解
給与明細は、次のような3つのセクションで構成されています。
| セクション | 主な内容 |
|---|---|
| 支給項目 | 基本給、残業手当、通勤手当、各種手当など |
| 控除項目 | 社会保険料、税金(所得税・住民税)など |
| 差引支給額 | 「手取り」の金額(実際に振り込まれる額) |
📌 控除項目とは?なぜ差し引かれるの?
控除とは、「社会的・法律的に必要な費用」を給料から自動的に差し引く仕組みです。
会社が代行して国や自治体に納付してくれています。
📘 控除項目ごとの解説
| 項目名 | 内容 | 概要 | 労使負担 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 医療費補助・出産手当金 | ケガ・病気・出産時に使える | 会社と本人で折半 |
| 介護保険 | 要介護時の保障 | 40歳以上が対象 | 会社と本人で折半 |
| 厚生年金 | 老後の生活保障 | 将来の年金に反映 | 会社と本人で折半 |
| 雇用保険 | 失業給付・育児休業給付 | 働けない時期を支える | 主に本人負担(会社も一部) |
| 所得税 | 国に納める税金 | 年末調整で精算される | 全額本人負担 |
| 住民税 | 地方に納める税金 | 教育・インフラ等に使われる | 全額本人負担 |
👉 健康保険・年金などは「労使折半(会社が半分負担)」なので、実は企業も同額を支払ってくれているんです!
💡 モデルケース:月収40万円の独身会社員(東京都)
diffコピーする編集する総支給:400,000円
【控除額(概算)】
- 健康保険:20,000円
- 厚生年金:36,000円
- 雇用保険:1,200円
- 所得税:6,500円
- 住民税:15,000円
▶ 控除合計:約78,700円
▶ 手取り:約321,300円
※扶養なし/賞与なしの月例モデルで算出
※協会けんぽ・国税庁源泉徴収税額表・住民税は総務省標準10%で概算
👪 共働き&扶養ありのケースはどうなる?
✅ 妻がパート・子ども2人のケース
- 配偶者控除:最大38万円
- 扶養控除(16歳以上):子ども1人あたり38万円
👉 所得税・住民税の負担が軽くなり、手取りがやや増える傾向に。
ただし、16歳未満の子どもには扶養控除がつかないため注意。
🧾 給与明細と源泉徴収票のつながり
毎月の控除は、年末調整や確定申告のベースにもなっています。
年末にもらう「源泉徴収票」では、以下のように整理されています:
| 給与明細 | 源泉徴収票の項目 |
|---|---|
| 支給総額 | 支払金額 |
| 所得税合計 | 源泉徴収税額 |
| 社会保険料合計 | 社会保険料等の金額 |
| 差引支給額 | 手取り(参考) |
👉 控除を把握しておけば、「源泉徴収票の読み方」も理解しやすくなります!
📊 控除項目が家計に与える影響
- ✅ 家計管理で「可処分所得(=手取り)」を正しく見積もれる
- ✅ 資産形成や積立投資の予算をリアルに設計できる
- ✅ 住宅ローン審査・保険設計時の見込み収入を判断できる
💬 手取りを増やすための視点
控除は義務ですが、以下のような対策で「手取りの改善」は可能です:
- NISAやiDeCoで節税しながら資産形成
- 年末調整で控除漏れをチェック(保険料控除など)
- 扶養控除・配偶者控除の活用を見直す
- 残業代に依存しすぎない働き方の工夫
✍️ まとめ
給与明細の「支給額」だけでなく、「控除欄」をしっかり見ることは、
未来の自分への“備え”にもつながります。
普段は流し見してしまいがちな明細、
今月は一緒にじっくり見直してみませんか?
⚠️ 免責事項
本記事は一般的なシミュレーションと公開情報をもとに構成しています。
社会保険料や税額は、加入制度・自治体・家族構成・年収・勤め先によって異なる場合があります。
具体的な金額や手取りは、各種明細や税務署・社会保険事務所など公的機関にてご確認ください。
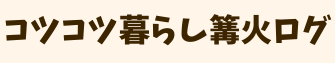



コメント