Part0:40代から始める資産形成
将来のお金のこと
40代に入ってからというもの、将来の「お金」のことを考える時間が一気に増えました。
子どもはまだ小学生と幼稚園。成長とともに教育費も増えていきます。
住宅ローンの返済も残っているし、離れて暮らす両親のことを考えれば介護の可能性も出てくる。
さらに自分と妻の老後資金も準備しておかなければならない…。
まさに「人生の三大出費が重なって押し寄せてくる」タイミングに直面しているのを、ひしひしと感じています。
貯金だけでは守れないと気づいた瞬間
正直なところ、40歳を過ぎるまで投資なんてほとんど考えていませんでした。
「とにかく貯金しておけば大丈夫だろう」と思っていたんです。
でも、ある日ニュースで「物価上昇率は2%台」と聞いたときに、とても不安になりました。
普通預金の金利は 0.001%。100万円預けても利息は10円。
一方で物価が2%上がれば、100万円の価値は実質98万円に目減りしてしまう。
「このままだと、せっかく貯めたお金が目に見えない形で減っていく……」
──そんな現実を突きつけられ、初めて「貯金だけでは守れない」と気づいたのです。
投資を始める勇気をくれたのは「NISA」
とはいえ、投資と聞くと「損したらどうしよう」という不安が先に立ちます。
実際、株やFXで大きな損をした知人の話も耳にしていたので、漠然と怖いイメージがありました。
そんな中で出会ったのが NISA(少額投資非課税制度) でした。
- 利益にかかる税金がゼロになる
- 少額から始められる
- 毎月自動で積み立てできる
これなら「投資の知識ゼロの自分でもできるかもしれない」と感じました。
さらに調べていくと、NISAはもともと 2014年に始まった制度 で、
イギリスのISA(個人貯蓄口座)をモデルにした「日本版ISA」だと知りました。
しかも、2024年からは「新NISA」として制度が大幅に拡充され、
これまでよりもはるかに使いやすくなっていたのです。
「よし、これなら自分も挑戦してみよう」
──そんな気持ちに背中を押されたのを今でも覚えています。
「40代から始めても遅くない」と確信した理由
最初に思ったのは「でももう40代、今さら遅いのでは?」という不安でした。
けれども数字を計算してみると、考え方が変わりました。
仮に毎月5万円を20年間、年利5%で積み立てた場合──
最終的な資産は約2,000万円。
「あと20年」あることは、むしろ大きなチャンスだと気づいたんです。
- 収入は20代の頃より安定している
- 少額からでも積立を続ければ複利が効く
- 今から準備すれば老後に間に合う
つまり、40代こそ「最後に巻き返せる世代」 なんです。
資産形成のベースとしてのNISA
このブログでは、私自身が実際にNISAを始めて学んだことをもとに、
- NISAの基礎知識
- 実際の始め方(証券口座開設から積立設定まで)
- 楽天経済圏を使ってお得に運用する方法
を、できるだけかみ砕いて解説していきます。
もしあなたも「投資はよく分からない」「自分にできるか不安」と思っているなら、安心してください。
私も同じところからスタートしました。
一歩踏み出せば、お金は「ただ減っていく存在」から「あなたの未来を支えてくれる味方」に変わります。
今日から一緒に、資産形成を始めていきましょう。
Part1:NISAの基礎知識
NISAとは?(歴史と仕組み)
NISA(ニーサ)は、2014年にスタートした「少額投資非課税制度」です。イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルに、日本版ISAとして導入されました。正式名称は Nippon Individual Savings Account で、投資で得た利益に税金がかからないことが最大の特徴です。
通常、株や投資信託の利益には約20%の税金がかかりますが、NISAならそのまま利益を受け取れます。つまり、同じ投資をしても「NISAを使うかどうか」で手元に残る金額が大きく変わってきます。
課税あり vs NISA
| 利益額 | 通常口座 | NISA口座 |
|---|---|---|
| 100万円 | 税金:約20万円 → 手取り80万円 | 税金0円 → 手取り100万円 |
💡 同じ100万円の利益でも、NISAを使えば20万円の差。
この差が10年・20年と積み重なれば、資産形成の結果は大きく変わります。
旧NISAから新NISAへ(2024年〜)
従来のNISAは「一般NISA」と「つみたてNISA」に分かれておりどちらか一方しか使えませんでした。長期投資の投資信託の場合はつみたてNISA、個別株取引をする場合はNISAを選ぶといったかたちです。
また、非課税期間も異なっており長期投資をする場合はつみたてNISAを選ぶしかありませんでした。つみたてNISAをしている場合、個別株は課税対象の特定口座で売買していました。
| 旧NISA(~2023) | ||
|---|---|---|
| つみたてNISA | 一般NISA | |
| 非課税保有期間 | 20年間 | 5年間 |
| 制度 (口座開設期間) | 2023年末で買い付け終了 | |
| 年間投資枠 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額 (総額) | 800万円 | 600万円 |
| 投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託、ETF | 上場株式・ETF・REIT・投資信託等 |
| 投資方法 | 積立 | 一括・積立 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
| 両制度の併用 | 不可(どちらか一方しか利用できない) | |
| 売却枠の再利用 | 不可 | |
2024年から始まった新NISAでは、つみたてNISAと一般NISAが統合され大幅にシンプルかつ柔軟に改善されています。
👉 制度が一本化され、長期投資に最適な仕組みになったことで、40代からの資産形成により安心して活用できるようになりました。
| 新NISA(2024~) | ||
|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 非課税保有期間 | 無制限 | |
| 制度 (口座開設期間) | 恒久化 (2024年からいつでも) | |
| 年間投資枠 | 360万円(合計) | |
| 120万円 | 240万円 | |
| 非課税保有限度額 (総額) | 1800万円 (うち成長投資枠1200万円) | |
| 投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託、ETF※1 | 上場株式・ETF・REIT・投資信託等※2 |
| 投資方法 | 積立 | 一括・積立 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
| 両制度の併用 | 可 | |
| 売却枠の再利用 | 可 (投資元本ベースの管理、枠復活は翌年) | |
※1金融庁の基準を満たした投資信託に限定
※2①整理・管理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
シミュレーションで見るNISAの効果
毎月5万円を20年間積み立て、年5%で運用できた場合のシミュレーションを比較します。
| 通常口座 | NISA口座 | |
|---|---|---|
| 積立総額 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 運用益 | 約850万円 | 約850万円 |
| 税金 | 約170万円(運用益の20%) | 0円 |
| 最終資産 | 約1,880万円 | 約2,050万円 |
💡 税金の有無だけで170万円の差。実際受け取れる資産がまったく違います。
NISAを使うメリットと注意点
メリット
- 利益に税金がかからない
- 少額(1,000円〜)から投資できる
- 自動積立で「ほったらかし投資」が可能
注意点
- 元本保証はない(短期的にマイナスになることも)
- 損益通算はできない(他口座の損益と合算不可)
- 短期売買や投機には向かない
NISAは初心者に最適な制度
- 「非課税 × 自動積立」で資産形成のスピードを加速できる
- 長期・分散・継続の3本柱を守れば安心
- 現金貯金では得られない“複利の力”を体感できる
Part2:投資の基礎を理解する
投資とは?貯金とどう違うのか
私たちが普段使う銀行預金の金利は、0.001%〜0.1%ほど。
100万円を1年間預けても、利息はせいぜい数百円です。
一方で、インフレ率は毎年2%前後。つまり「物価が上がるスピード > 預金の金利」で、現金だけを持っていると資産価値は目減りしていきます。
投資は「お金に働いてもらう仕組み」。
自分が汗を流して働くだけでなく、お金自身が増える仕組みを作ることが投資の本質です。
💡 たとえば
- 貯金=タンスに眠っているお金
- 投資=アルバイトをして稼いでくれるお金
投資の代表的な方法
投資と一口に言ってもさまざまな方法があります。40代からの資産形成に向いているのは、以下のような長期投資型です。
- 株式投資:企業の成長に投資。値動きは大きいがリターンも大きい。
- 投資信託:多くの銘柄をまとめて買える「分散投資」の代表格。初心者向けはインデックス投資。
- 債券投資:国や企業にお金を貸す仕組み。値動きが安定している。
- 不動産投資:家賃収入や値上がり益を狙う。ただし初期資金が大きめ。
投資にリスクはある?
投資には「価格変動リスク」があります。
ただし、投資の期間を長く取ることでリスクは下がるのが特徴です。
- 短期投資(1年以内):値動きに振り回されやすく、損失の可能性が大きい。
- 長期投資(10年以上):一時的に下がっても、時間とともに回復する傾向が強い。
📌 ポイント:長期で見れば、世界経済は右肩上がりで成長してきた歴史がある。
複利の力を知ろう
投資を長期で続けると「複利の効果」が働きます。
複利とは「利息が利息を生む」仕組みのことです。
シミュレーション例
100万円を年利5%で運用した場合:
| 年数 | 元本 | 運用益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1年後 | 100万円 | 5万円 | 105万円 |
| 10年後 | 100万円 | 約63万円 | 約163万円 |
| 20年後 | 100万円 | 約165万円 | 約265万円 |
💡 単利(毎年5万円ずつ増える)なら20年後は200万円ですが、複利運用では 265万円 に。
時間を味方にすることで、資産は加速度的に増えていきます。
投資の基礎は「長期・分散・積立」
- 長期投資:時間を味方につけることでリスクを減らせる
- 分散投資:投資信託を使えば少額で世界中に分散できる
- 積立投資:毎月一定額を積み立てることで「安いときに多く、高いときに少なく」買える(ドルコスト平均法)
👉 この3つを意識することが、40代からの資産形成を成功させる基本の型になります。
Part3:NISAの始め方ステップガイド
資産形成のベースしてNISAを使うことが有効だとわかったとおもいます。それでは、実際にNISAを始めるステップを説明します。
ステップ1:NISA口座を開設する
NISAを始めるには、まずNISA口座の開設が必要です。証券会社や銀行で開くことができます。
注意が必要なのは、NISA口座は、一人ひとつの金融機関でしか開けないという点です。年単位で金融機関を変更することはできるのですが、年の途中では変更できません。だからこそ、最初に選ぶ金融機関が重要になります。
多くの人にとっては各種手数料が安く、取り扱う金融商品の幅が広いネット証券がおすすめです。ネット証券は実店舗を持たず取引をネット上で完結できます。
ネット証券
- SBI証券
- 楽天証券
- 松井証券
- マネックス証券(NTTドコモグループ)
- 三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)
初心者の方にとってもっともおすすめなのは楽天証券です。
楽天証券を選ぶ理由
- ポイント投資が可能:日常生活で貯まる楽天ポイントをそのまま投資に使えるので、貯金感覚で投資を始められる。
- 楽天カード積立でポイント還元:毎月の積立に対して1%還元。例えば月5万円なら年間6,000ポイントが戻る=実質利回り上乗せ。
- 楽天銀行との連携:「マネーブリッジ」で普通預金金利が0.10%に(大手銀行の100倍水準)。投資だけでなく預金でもお得。
- シンプルで使いやすい:スマホアプリ「iSpeed」「iGrow」が直感的に操作でき、投資初心者でも迷いにくい。
👉 楽天証券+楽天カード+楽天銀行の三位一体の仕組みにより、「ポイント還元 × 金利優遇 × 投資の利便性」を同時に得られるのが最大の魅力です。
ステップ2:投資商品を選ぶ
NISA口座を開設したら、次は投資する商品を選びます。おすすめは低コストのインデックスファンドです。特に次の2つが定番です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):アメリカの代表的500社にまとめて投資。世界経済の中心「米国市場」に期待する人向け。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー):日本を含む世界中の株式に分散投資。1本で世界全体をカバーできる安心感。
👉 どちらを選んでも正解ですが、「米国集中で高成長を狙いたい」ならS&P500、「リスク分散を重視したい」ならオールカントリーがおすすめです。
ステップ3:積立設定をする
投資商品を決めたら、積立の設定を行います。ここでのポイントは「自動化」です。
- 毎月の投資額を決める:最初は無理のない金額から(月1万円でもOK)。
- クレジットカード積立を利用:楽天カードで積立を行えば1%ポイント還元。これだけで「プラスのリターン」を積み上げられる。
- 自動積立で継続:「ほったらかし投資」が可能。心理的に迷わず、長期で資産形成が続けやすい。
👉 この「自動積立 × ポイント還元」の仕組みを作ることこそ、資産形成を成功に導く最初のステップです。
Part4:楽天経済圏でのNISA始め方(手順+シナジー具体例)
楽天証券でNISA使う最大のメリットは「楽天経済圏との連携」です。単体で使うよりも、楽天カード・楽天銀行と組み合わせることで、投資効果を最大化できます。
ステップ1:楽天カードを作る
まずは楽天カードを作成しましょう。楽天カードを使ってNISAの積立を設定すると、毎月の投資額の1%がポイント還元されます。
| 投資額 | 年間のポイント還元 |
| 月3万円 | 3,600ポイント |
| 月10万円(上限) | 12,000ポイント |
👉 このポイントはそのまま投資に回せるので、「複利の力」でさらに資産形成を加速できます。
毎月の投資をクレカ払いにすることで、楽天ポイント還元を受けられます。
ステップ2:楽天銀行を開設する
次に楽天銀行です。楽天証券と「マネーブリッジ」という連携を設定すると、普通預金金利が0.28%にアップします(メガバンクの約200倍)。
- 資金移動がスムーズ(証券口座と即時振替が可能)
- 預金でも優遇金利が適用
- 日常使いの口座としても便利(ATMや振込手数料優遇あり)
👉 投資資金の置き場所としても、生活口座としても使いやすいのが楽天銀行の強みです。
マネーブリッジで金利優遇+自動入出金。証券口座との相性◎
ステップ3:楽天証券を開設する
最後に楽天証券を開設します。楽天カード・楽天銀行と組み合わせることで、次のような三位一体のシナジーが得られます。
- 楽天カード:クレジット決済で積立しながらポイント還元
- 楽天銀行:「マネーブリッジ」で金利優遇+資金移動がスムーズ
- 楽天証券:ポイント投資・アプリ連携・低コスト投資信託が充実
👉 つまり、日常の支払いから投資までをワンストップで完結させられるのが楽天経済圏の最大の魅力です。
ポイント投資+手数料無料でNISAに最適。
最初の一歩におすすめ!
楽天経済圏で投資を“習慣化”する
楽天カードで支払う → 楽天ポイントが貯まる → 楽天証券で投資に回す → 楽天銀行で資金を効率的に管理、という資産形成のサイクルが自然に回り続けます。
この「仕組み化」こそが、40代からの資産形成を成功に導くカギです。無理なく、生活に溶け込む形で投資を続けられます。
Part5:NISAの運用と続け方(ドルコスト平均法・長期投資の考え方)
口座を開設し、積立設定をしたら、次に大切なのは「続けること」です。投資は短期で結果を出すものではなく、長期でコツコツ積み上げてこそ成果が出ます。
ドルコスト平均法のメリット
NISAの積立投資でよく使われるのが「ドルコスト平均法」です。これは毎月一定額を投資することで、価格が高いときは少なく、安いときは多く購入する仕組みです。
| 株価が高いとき | 少ない口数を購入 |
| 株価が安いとき | 多くの口数を購入 |
👉 これにより、購入単価が平準化され、短期的な値動きのリスクを和らげる効果があります。
「続ける」ための工夫
- 自動積立設定:強制的に投資を続けられる環境を作る
- 無理のない金額:月1万円でも十分。家計に負担をかけない範囲でOK
- 投資額の調整:厳しいときは減額、余裕があるときは増額で柔軟に
特に40代から始める場合、教育費や住宅ローンなど支出も多い時期です。投資を「続けられる仕組み」にすることが成功のカギです。
短期の値動きに惑わされない
投資信託や株価は日々動きます。時には下がることもありますが、そこで焦って売却するのはNGです。大切なのは「長期視点」を持つこと。
過去のデータを見ても、株式市場は短期では上下を繰り返しますが、長期では右肩上がりに成長してきました。NISAを使うことで、この成長の果実を税金なしで受け取れるのです。
長期投資のイメージ
たとえば月3万円を20年間積み立てた場合、元本は720万円です。しかし、年利5%で運用できれば、20年後には約1,200万円以上に増える可能性があります。
👉 複利の力を最大限に活かすためには、「長期」「継続」「分散」がポイントです。
投資は“続ける仕組み”を作った人が勝つ
NISAを使った資産形成で一番大切なのは、「無理なく、長く続けること」です。ドルコスト平均法を活用し、短期の値動きに振り回されず、20年先を見据えてコツコツ積み立てていきましょう。
Part6:楽天証券の便利ツール活用(iSpeed・iGrowなど)
積立投資は「仕組み化」することで継続が容易になります。楽天証券には、投資を無理なく続けられるようにサポートするツールが揃っています。ここでは特に便利な iSpeed と iGrow を紹介します。
iSpeed(楽天証券アプリ)
iSpeed は楽天証券が提供する公式アプリで、株式や投資信託の確認・取引がスマホで簡単にできます。特に忙しい40代の方には「手軽に確認できる」ことが大きなメリットです。
- 積立設定の確認・変更がスマホからできる
- 投資信託の評価額をワンタップでチェック
- マーケットニュースやチャートの閲覧も可能
👉 朝の通勤中や夜のすき間時間にサッと確認できるので、投資を生活に自然に組み込めます。
iGrow(初心者向け投資サポート)
iGrow は、投資初心者向けに資産形成をナビゲートするサービスです。質問に答えるだけでおすすめの投資信託を提案してくれるので、「どのファンドを選べばいいの?」という悩みを軽減してくれます。
- いくつかの質問に答えるだけで投資プランを提案
- リスク許容度に合わせたファンドが自動表示
- そのまま積立設定につなげられる
👉 「迷って進めない」を解消し、投資の第一歩を踏み出しやすくしてくれるのがiGrowです。
ツール活用で「投資を習慣」に
せっかくNISAを始めても、放置して不安になったり、逆に気になりすぎて売買を繰り返すのはよくありません。iSpeedやiGrowを活用して、「確認は簡単に、判断はシンプルに」を心がけると、長期投資が続けやすくなります。
つまり、ツールは「投資の習慣化」を助ける存在。自分のライフスタイルに合わせて賢く取り入れていきましょう。
Part7:安心して投資を続けるために
NISAを始めたばかりの初心者がつまずきやすいのは、「焦って短期で結果を求めること」「途中で不安になってやめてしまうこと」です。ここでは安心して投資を続けるためのコツと、私自身の実例、さらにNISAと相性のよい制度、そして初心者からよくある質問をまとめました。
初心者が失敗しないためのコツ
- 少額から始める:まずは毎月1万円からでもOK。生活に負担をかけず続けられる額を設定しましょう。
- 長期で続ける:5年・10年というスパンで考えることが大切。短期的な値動きに一喜一憂しないこと。
- 分散投資を心がける:銘柄・地域・時間を分散することでリスクを抑えられます。
- ニュースやSNSに振り回されない:「暴落」「急落」という言葉に惑わされず、積立を止めないことが最も重要です。
実例:私のNISA投資
私自身もNISAを活用して資産形成をしています。実際の投資スタイルを少しご紹介します。
- 毎月10万円を4つの投資信託に分散(S&P500・オールカントリーなど)
- 楽天カードによるクレジットカード積立でポイント還元をフル活用
- 暴落があっても積立は止めず、必要なら投資額を一時的に減らして継続
このように「自動で続ける仕組み」を作っておけば、感情に左右されずコツコツと資産形成を進めることができます。
NISAと併用したい制度
- iDeCo:老後資金を作りながら所得控除で節税できる。NISAと並行して活用するとより安心。
- ふるさと納税:節税しつつ返礼品がもらえるお得な制度。家計の負担を軽減。
- 保険の見直し:必要以上の保険を削減して投資資金に回す「攻めと守り」のバランスが大切。
よくある質問Q&A
初心者の方からよくいただく質問をまとめました。
- Qいくらから始めればいい?
- A
最低100円から可能。おすすめは毎月1万円からの積立。
- Q損をしたらどうなる?
- A
元本割れのリスクはあるが、長期・分散でリスクを軽減できます。
- Q途中でやめられる?
- A
いつでも解約可能。ただし長期で続けるのが基本。
- QiDeCoとどちらを優先?
- A
流動性を考えるとまずはNISAがおすすめ。余裕があればiDeCoも併用。
- Q夫婦で使える?
- A
夫婦それぞれがNISA口座を持てます。家庭で2倍の非課税枠が活用可能。
- Q投資信託は何を選べばいい?
- A
低コストのインデックスファンド(オールカントリー・S&P500など)が無難。
- Q積立額は途中で変更できる?
- A
可能。家計の状況に合わせて増減できます。
- Q口座はどこで作るべき?
- A
ネット証券(特に楽天証券)が低コスト&サービス連携でおすすめ。
- Q暴落のときはどうする?
- A
積立を止めず継続。むしろ買い場になることもあります。
- Q退職金やボーナスはNISAに入れられる?
- A
年間投資枠の範囲内なら一括投資も可能。
- Q他の証券会社に移せる?
- A
ロールオーバーや金融機関変更の手続きが可能です。
これらを押さえておけば、不安や疑問で立ち止まることなく、安心して投資を続けられるはずです。
まとめ|40代からの資産形成は「今すぐ」始めよう
40代からの資産形成において、NISAはもっとも取り組みやすく効果的な制度です。
現金だけで資産を持つことはインフレや為替変動のリスクを抱えることになりますが、NISAを活用すれば税制優遇を受けながら投資を続けられ、将来に備えることができます。
今回ご紹介したように、楽天証券を中心とした楽天経済圏を活用すれば、
「証券口座+楽天カード+楽天銀行」というシナジーで、ポイント還元や資金管理のしやすさまで手に入ります。
資産形成で最も大切なのは「早く始めること」と「無理なく長く続けること」です。
金額は少額でも構いません。自動で積み立てる仕組みを作り、日常生活に負担をかけずに投資を続けていきましょう。
資産形成の3ステップ
- 楽天カードを作り、毎月のクレジットカード積立を設定する
- 楽天銀行を開設し、証券口座とのマネーブリッジで金利優遇を受ける
- 楽天証券でNISA口座を開設し、S&P500やオールカントリーなどの低コスト投資信託を設定する
この3ステップを実行すれば、あなたのNISA資産形成はもうスタート地点に立てます。
将来の安心のために、今日から一歩を踏み出してみませんか?
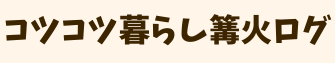



コメント