手取りと年収のリアルを一緒に学ぶ 第5回
今回は、「年収」と「所得」の違いについて。
なんとなく聞いたことはあるけれど、ちゃんと説明できるかというと…?
✅ 年収と所得ってどう違うの?
✅ 税金計算に使うのはどっち?
✅ 所得って自分にも関係ある?
そんな疑問を、私自身の学びとともにひもといていきましょう!
🔰 年収・所得・手取りって何が違うの?
まずはこの3つの言葉をざっくり整理しましょう。
| 用語 | 意味 | 主に登場する場面 |
|---|---|---|
| 💼 年収 | 会社から支給される合計額(総支給) | 給与明細、転職サイト、求人 |
| 💰 所得 | 年収から「必要経費」や「所得控除」を引いた額 | 税金の計算、扶養の判定 |
| 🏠 手取り | 実際に振り込まれる額(税・保険料を引いた残り) | 家計管理、生活費の見積り |
📌 所得は、税金を計算するための“スタート地点”になる金額です。
📊 所得の正体とは?
会社員の場合、所得の計算式は以下の通りです。
コピーする編集する所得 = 年収 - 給与所得控除 - 所得控除
たとえば…
- 年収500万円の人の場合
➤ 給与所得控除:約100万円(自動で引かれる)
➤ 所得控除(社会保険料・基礎控除など):約120万円
textコピーする編集する所得 ≒ 500万円 - 100万円 - 120万円 = 280万円
📎 この「280万円」が、所得税・住民税などの課税対象となる金額になります。
🧾 所得控除ってなに?どんな種類がある?
所得控除は「税金を軽くしてくれる仕組み」。
代表的なものを一覧にすると、こんな感じです。
| 控除の種類 | 内容 |
|---|---|
| 🧍♂️ 基礎控除 | すべての人が受けられる(48万円) |
| 🏥 社会保険料控除 | 健康保険・年金・雇用保険など |
| 👨👩👧👦 扶養控除・配偶者控除 | 家族がいる場合に使える |
| 🪙 生命保険料控除 | 保険料を支払っている場合に適用 |
| 🧓 iDeCo控除 | 老後資産を積立している場合に有効 |
💡 控除が増えれば増えるほど「所得」が小さくなり、支払う税金も少なくなります。
👀 所得が重要な理由【3つの視点】
① 税金の金額が変わる
所得税や住民税は、所得額×税率で計算されます。
つまり、所得が低ければ税金も低くなります。
② 各種制度の対象に関係する
- 児童手当、高等教育無償化、保育料の軽減 など
➤ いずれも「所得が○○万円以下」が条件
つまり、所得が数万円変わるだけで制度の対象になる/外れることも。
③ 節税の戦略を立てやすくなる
「ふるさと納税」や「iDeCo」など、控除を増やして節税するには所得の把握が不可欠です。
🧑🏫 所得と会社員・自営業の違いも知っておこう
| 立場 | 所得の計算方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 会社員 | 年収から自動計算(給与所得控除+所得控除) | 仕組みがシンプル、源泉徴収あり |
| 自営業 | 収入-経費-所得控除 | 経費の幅が広く節税しやすいが、確定申告が必要 |
会社員でも、副業を始めたら自営業扱いになる可能性もあるので、理解しておくと安心です。
📎 給与明細・源泉徴収票とどう違う?
給与明細や源泉徴収票には「支給額」や「控除額」は出ますが、
「所得」という項目は直接書かれていません。
源泉徴収票の「課税対象所得(所得控除後の金額)」がそれに相当します。
❌ よくある勘違い
「年収が500万円なら、使えるお金も500万円でしょ?」
実際は…
- 手取り:370〜380万円前後(家族構成により変動)
- 所得:280〜300万円前後(控除により変動)
✅ 控除を意識していないと、「税金が多すぎる!」と感じてしまうことも…
📝 まとめ
- 「年収」と「所得」は別物!所得は税金の出発点
- 所得は「年収-給与所得控除-所得控除」で決まる
- 所得がわかると、節税・制度活用・家計の見直しに役立つ
- 所得控除の活用が、税負担をやわらげる大きなカギ!
🔜 次回予告(第6回)
📌 「年収が上がったのに、手取りが増えないのはなぜ?」
── 税率・控除・“壁”の仕組みを一緒に深掘りしていきましょう!
🧷 免責事項
本記事は2025年7月時点の法制度に基づいて作成しています。
各種控除や課税額は、個人の状況・自治体によって異なります。
正確な情報は税務署・公式サイト等をご確認ください。
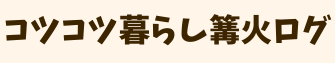



コメント