「節税って、お金持ちだけの話じゃないの?」
そんなふうに思っていた時期が私にもありました。
でも実際は、会社員でも主婦でも、自営業でなくても。
日々の暮らしの中でできる「節税対策」は意外とたくさんあります。
今回は、iDeCoはやってないけれどNISAは活用中の私が、自分自身の体験も踏まえて、
初心者向けにわかりやすく節税方法をまとめました。
✅ 節税対策ってそもそも何?
まず前提として、節税とは法律のルール内で税負担を軽くすることを指します。
節税というと難しそうに感じるかもしれませんが、
- 国や自治体が用意した制度を
- 正しく利用して
- 払わなくてよい税金を減らす
というシンプルな考え方です。
たとえば、ふるさと納税のように「寄付したお金が税金から控除される」ケースもあれば、
NISAのように「投資で得た利益が非課税になる」仕組みもあります。
✅ まずはこれ!個人でできる節税対策5選
ここでは、私たち個人が比較的始めやすく、家計にもメリットを感じやすい5つの節税対策を紹介します。
| 対策 | 内容 | 節税効果 |
|---|---|---|
| ① ふるさと納税 | 好きな自治体に寄付すると返礼品&税控除が受けられる | 数千円〜数万円/年 |
| ② NISA(新NISA) | 運用益が非課税になる制度。投資初心者にもおすすめ | 長期で大きな節税 |
| ③ 医療費控除 | 年間10万円以上の医療費がかかった場合に使える控除 | 数千円〜数万円 |
| ④ iDeCo | 掛金が全額所得控除。将来の年金資金にもなる | 毎年の税額が軽減 |
| ⑤ 確定申告での控除 | 住宅ローンや副業経費なども控除対象になることがある | 効果はケース次第 |
✅ 実際どうなの?|やってみて感じたメリットと注意点
ここからは、私自身が実際に取り組んでいること・まだ導入していないことを正直に紹介します。
| 対策 | 節税効果 | 手間 | 実際の対応と感想 |
|---|---|---|---|
| ふるさと納税 | 年1〜2万円以上 | 中 | 毎年実施。返礼品は水や米など生活必需品に。特に楽天ふるさと納税はポイント還元もありお得感が強い。2025年10月の制度変更前の活用がおすすめ。 |
| NISA(新NISA) | 長期で大きい | 低 | 毎月10万円つみたて中。放置型でも問題ない設計でラク。制度のわかりやすさも魅力。 |
| 医療費控除 | 年による | 中 | 我が家の自治体では子どもの医療費が無料なので、なかなか10万円を超えない。家族分の領収書管理が意外と大変。 |
| iDeCo | 所得控除大 | 高 | 我が家は導入していない。60歳まで引き出せない資金拘束がネックで、NISAを優先。節税効果は高いが、人によって向き不向きあり。 |
| 確定申告 | 数万円規模 | 中 | 住宅ローン控除のため毎年対応。副業収入が増えてくれば、経費処理も含めた見直しが必要になりそう。 |
節税=「必ずやったほうがいい」というより、
**「自分の家計やライフスタイルに合う方法を選ぶ」**ことが重要だと感じています。
✅ どれから始めればいい?
正直、すべてをいきなり始めるのは大変です。
まずは次の2つから着手するのがおすすめです。
🌟 ふるさと納税:節税+実利を得られる制度
- 所得に応じて年間の寄付上限が決まっている
- 自己負担2,000円で返礼品がもらえる
- 寄付分は住民税・所得税から控除
忙しい人でも「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告不要。
寄付先の自由度が高く、地方応援にもつながるお得な制度です。
🌟 新NISA:投資利益に税金がかからない
- 投資で出た利益に対して通常20.315%の税金が非課税
- つみたて投資枠+成長投資枠を併用可能
- 長期的な資産形成に非常に向いている制度
つみたて設定して放置できる仕組みのため、投資初心者でも始めやすい点がメリットです。
✅ 節税は「知ってる人が得をする」分野
今回紹介した5つの対策は、すべて国が制度として用意しているものです。
- 「知らなかったから使ってなかった」
- 「難しそうで後回しにしていた」
こういった理由で逃してしまうのは、正直もったいないです。
実際に私自身も、「iDeCoってそんなに節税できるんだ」と知ったのは、かなり後からでした。
でも、生活スタイルや将来設計を考えたとき、iDeCoよりもNISAを優先するという判断をしています。
✅ まとめ|できることから、コツコツと
節税対策は、「一気にやる」よりも「できることから始める」が基本です。
- 家計が苦しいからこそ、お金の出入りに敏感になる
- 子育て世帯だからこそ、将来を見据えて仕組みを活用する
こういった視点で、「自分に合った節税」を見つけていきましょう。
時間が味方になってくれる制度も多いので、早く知って、早く始めるのが最大の節税です。
⚠ 免責事項
本記事は個人の経験・調査に基づいて作成されたものです。
制度内容は変更されることがありますので、実際の申請・判断は税務署や金融庁、専門家などの公的情報を参考にしてください。
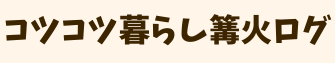

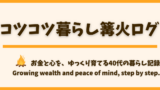

コメント